いろんなバージョンのLinuxをUSBメモリにいれる方法を説明します。各Linuxの違い、32bit版、日本語化の手順も書きました。動画作成フリーソフト9VAeきゅうべえの Linux版開発に利用しています。Windowsのストレージを使わないのもメリット(使うこともできる)。
- Linuxの入手
- Linux起動USBメモリの作り方(Windows用)
- パソコンの起動順序の変更
- Linux Mintの日本語化
- Linux Mint のファイル共有
- FFmpeg / mpg321 のインストール
- midori / Chrome のインストール (Ububtu)
- ChromeOS Flex
- 9VAeのインストール、しゃべる解説動画の作り方
- 解説動画の作り方
Linuxの入手
下から、linux の .ISO ファイルをダウンロードします
- Ubuntu (最初から日本語が使える。64bit用)
- Linux Mint (軽い。各種ツール(ffmpeg,mpg321,OpenJTalkなど)が使える。32bit版あり)
- Puppy Linux(軽い。日本語化がむずかしい、日本語32bit版もあり)
中古Windows(XP/7/Vista/8など)は 32bit版でないと動かないかもしれません

● Ubuntu ダウンロード
● LinuxMint ダウンロード
- ここを開く。「Download」をクリック
- Cinnamon がおすすめ。「Download」をクリック
- いろんな場所からダウンロードできます。とりあえず「World-LayerOnline」をクリック
- ダウンロードが終わると、ダウンロードフォルダにISOファイルができます。
● Puppy Linux ダウンロード
- ここを開く。
- Windows 32bit 用は「Ubuntu bionic x86-32bit BionicPup32 8.0」の右側の Main をクリック。ダウンロードフォルダにISOファイルができます。
各Linux Version の違い
| OS | Version | memo |
| Ubuntu | 16 | 32bit版あり ffmpegが使えない |
| Ubuntu | 18 | ffmpegが使えない |
| Ubuntu | 20 | ffmpegが使えない。Firefoxが動く |
| Ubuntu | 21 |
ffmpegが使える。32bitだと動かない |
| Ubuntu | 22 |
ffmpegが使える。32bitだと動かない |
| Mint | 18 |
軽い。 32bit版あり。●開発者向き、9VAe開発に使用 Geany Debuggerが使える |
| Mint | 19 | 32bit版あり Geany Debuggerが動かない |
| Mint | 20 |
Geany Debuggerが動かない |
| Mint |
21 21.1 21.2 |
●軽くて初心者におすすめ。 ffmpeg, mpg321, Geany Debuggerが使える |
| Puppy Linux | 5 | 日本語32bit版あり libgtk-3 がないので9VAeがうごかない |
| Puppy Linux | 8 | 32bit版あり ffmpegがはいっている。日本語フォントがない。 |
| ChromeOS Flex | - | Chrome拡張機能でUSBを作成。Chromebook互換。Googleドキュメントなど、ブラウザアプリを使うならおすすめ。 |
Linux起動USBメモリの作り方(Windows用)
- 8GB以上の USBメモリをパソコンにさします。SDカード+アダプタでもOK。
- Universal-usb-installer をここから下のようにダウンロードします。
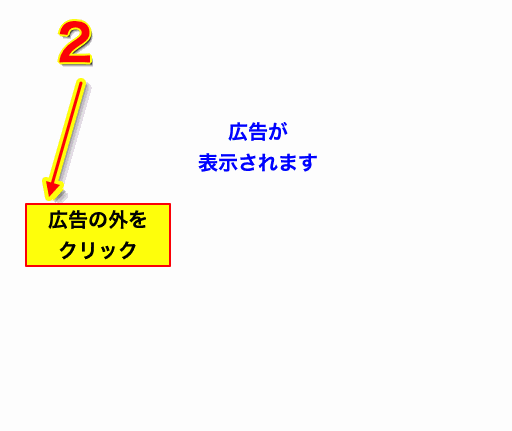
- 広告のダウンロードを避けて「Download UUI」ダウンロードボタンを押します。
- 広告が表示されますが外を押して消すとダウンロードできています。
- ファイルエクスプローラを実行(Windowsボタンと「E」を同時に押す)「ダウンロード」フォルダをひらくと、なかにダウンロードできているはずです
ダウンロードしたアプリを実行。USB作成アプリが起動します。
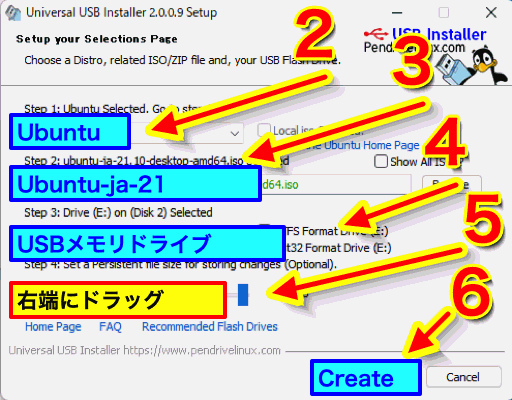
- I Agree (了解)
- インストールするOSを選択
- ダウンロードしたOSを選ぶ
- 書き込むUSBドライブを選ぶ
- USB上のユーザーエリアサイズ。右端に設定するとよい
- Create(作成)
これでUSBメモリの作成がはじまります。できたUSBメモリをパソコンにセットし、再起動します。USBメモリから起動できる設定になっていれば、Linuxが起動するはずです。
パソコンの起動順序の変更
- USBメモリを Windows パソコンにセットし、再起動します。Chromebookでは起動しません。古い32bitWindowsパソコンでは、32bit版Linuxでないと動きません。Linux Mint 32bit版はこちら(32bitタブ)
- 起動順序の変更が必要な場合もあります。起動直後の画面下に表示されているキーを押して、パソコンの起動順序の設定を変更します。たとえば、F2キーを押しながら再起動するなど・・・機種によってキーは違います
- 起動設定画面が表示されたら、画面の説明に従って、起動の順番を変更します。USBメモリをHDD(ハードディスク)より先に起動するようにします。
Linux Mintの日本語化
Linux Mint は起動が速く、動作が軽くておすすめですが、日本語を自分で追加する必要があります。Mintを起動してから以下のように設定します。
- (日本語キーボードの場合)左下Mintボタン>Preferences>Keyboard。上の「Layouts」をクリック。左下の「+」をクリック。「Japanese」を選んで「Add」ボタンをクリック。メニューバーの右端の国旗で、英語、日本語キーボードが切り替えできるようになります。
- 左下Mintボタン>Preferences>Languages。下の「Add」ボタン(ない場合はInstall/Remove Languagesで「Add...」)「Japanese, Japan(UTF-8)」をリストに追加。日本国旗を選んで、下の「Install langage packs」ボタンで日本語が追加されます。エラーが出た場合でも、追加モジュールを「install」すれば日本語化できました。
- 「Language」の右側の「C.UTF-8」をクリック。「Japanese」をクリック。
- 左下Mintボタン>Preferences>Input method。左側の「Japanese」をクリック
- こんにちはの下の「Install」ボタンをクリック。日本語入力に必要なソフトが追加されます。上の[None▼]をクリックして「Fcitx」に設定。再起動。(Mint18の場合は「Fcitx」の右側の「Add Support for Fcitx」をクリック。もう一度クリックしオプションもインストール、「Input method」の右側の None を「Fcitx」にセット)
- いったん再起動(左下Mintボタン>電源ボタン>Restart)。Mint21の場合、以下の作業は不要でした。●再起動時のあとファイル名を変更するかたずねられたら「古い名前のまま使う」がよいでしょう。デスクトップなどが日本語になると使いにくくなります。
- 左下Mintボタン>Preferences(設定)>Fcitx configuration(設定)。入力メソッドの中に「Mozc」が必要。日本語キーボードの場合は、「キーボード-日本語」も必要。もしなければ、下の「+」をクリックして追加します。
- Only Show Current Language のチェックをはずす
- 下の箱に「Japanese」といれて検索(J は大文字)
- 「Keyboard - Japanese」をクリック(または キーボード日本語)
- 「OK」ボタンをクリック>リストの中に「Keyboard - Japanese」が追加されます。※もし英語キーボードなら Keyboard - Japanese 追加の作業は不要です。
- 「Keyboard - Japanese」を選び、下のツールボタン「^」をクリックして一番上に移動させます。これで日本語キーボードからの直接入力が標準になります。
- 下のツールボタン「+」をクリック
- 下の箱に「mozc」といれて検索
- 「Mozc」を選択し「OK」ボタンをクリック
- 「Mozc」行を選択し「^」ボタンをクリックして上から2番目に移動させます。コントロールキーとスペースキーを同時に押すと日本語入力切替できます。
- こちら XtraPCの日本語化も参考になります。
Mozc 辞書登録
「Mozcの設定」で辞書登録できます。ない場合は、ターミナルから mozc-utils-gui をいれます。
- ツールバーの黒いボタン「ターミナル(端末)」を開き、以下の命令をキーボード入力して実行。最初に update で更新しておくとよいです。
-
sudo apt-get update
-
sudo apt-get install mozc-utils-gui
これで「Mozcの設定」が追加されます。 - 左下「メニュー」ボタン>「設定」>「Mozcの設定」
- 「辞書」タブ。「ユーザ辞書の編集」
- よみ、単語を表に追加すれば辞書登録されます
Linux Mint のファイル共有
LinuxMint のフォルダを Windows から見えるようにする方法です
ターミナルを使って Samba をいれる
- ツールバーの黒いボタン「ターミナル(端末)」を開き、以下の命令をキーボード入力して実行
-
sudo apt-get update
これでツールを更新します -
sudo apt-get install samba samba-common-bin
Sambaがはいります。
Samba の設定ファイルの修正
- ターミナルから以下の命令で設定ファイルを開きます。nano はテキストエディタ
-
sudo nano /etc/samba/smb.conf
- [global]の下に max protocol を1行追加(Windowsで見えるようにするため)
[global] max protocol = SMB2
- ファイルの最後に次の[share]を追加
[share] comment = mint share writable = yes path = /home/mint force user = mint
- Ctrl+O で「smb.conf」を上書き保存
- Ctrl+X で「nano」を終了
samba パスワードの設定
- ターミナルから以下の命令でパスワードを設定
sudo smbpasswd -a mint
パスワードを2回入力します
samba 再起動
-
sudo service smbd restart
Windows / Mac からの接続方法
- Mint ツールバー右端のネットワークボタンを押して「ネットワーク設定」を開きます
- 中に「192.168.xxx.xxx」といった4つの数字(IPV4アドレス)が書かれています(先頭が192でないこともあります)。この数字が端末のアドレスになります。
- Windows からは、エクスプローラのアドレスバーに上の4つの数字を以下のようにいれてフォルダを開きます。
¥¥192.168.xxx.xxx
ユーザー名「mint」と設定したSambaパスワードをいれるとLinuxフォルダが見えるはずです。 - Mac からは、Finder メニュー>移動>サーバーへ接続 で以下のようにいれて「接続」ボタンをクリックします。
smb://192.168.xxx.xxx
名前を「mint」にしてSambaパスワードを入れます。
別の Linux からの接続
mount 命令で mint と接続するのですが、その命令をいれたフォルダをデスクトップにつくっておくと簡単です。
- デスクトップに open-mint というフォルダを作成し、以下の中身の mount.sh というファイルを入れておく
#!/bin/sh sudo mount -t cifs //192.168.xxx.xxx/mint /home/desktopのパス/open-mint -o user=mint,sec=ntlmssp,nounix,noperm,rw
意味は、ネットワークアドレス 192.168.xxx.xxx の mint フォルダを、デスクトップの open-mint フォルダに割り当てるという意味です。 - mount.sh を実行可能に設定。これを実行し、 Linuxのパスワード、mint の samba パスワードを入れると、open-mint フォルダの中が mint になります。
Linux Mint をプログラム開発に使う場合、こちらも参考。
Android のデータを Linux に転送する
- スマホと Linux を USB ケーブルで接続。(充電しかできないケーブルは不可)
- スマホ「設定」(歯車アイコン)をタッチ
- 「接続済みのデバイス」をタッチ
- 「USB」をタッチ
- 「ファイル転送」をタッチ
- Linux「ファイル」アプリを起動すると、左側にスマホが表示されるはずです。それをクリック
- 「内部共有ストレージ」をクリック。これでスマホの中のファイルがみえるので、コピーできます。スマホの写真は「DCIM」フォルダの中にあります。スマホ版9VAeに画像や音楽を入れるには「Download」フォルダの中の「9VAe」フォルダに転送します。
Puppy Linux (BionicPup32)の日本語化
起動後のQuick Setupで設定
- Countryの最初:ja_JP Japanese,Japan
- UTF-8 encoding にチェック
- 時刻:GMT+9 (Tokyo)
- キーボード:jp Japanese(英語キーボードなら English(US))
- OKを2回クリック
- 日本語パックのインストールが必要。日本語フォントがないので日本語が表示できない。ここに日本語化の記事あり
- 最初の終了時に PuppyLinux に加えた変更を保存する場所を作成する必要がある(英語の説明にしたがってUSBメモリ上に作成する)。
FFmpeg / mpg321 のインストール
フリーソフト9VAeで動画出力するには、ffmpeg が必要です。mpg321 があれば、mp3 音楽が再生できます。
- Linuxはターミナルから命令を入力することで、いろんなツールを導入できます。
- ターミナルは、メニューバーや、アプリ>ユーティリティなどの中にあります。
- ターミナルで以下の命令を実行し、ffmpeg をインストールします。
sudo apt-get -y install ffmpeg
- インストールできなかった場合以下の命令をお試しください。(/snap/bin/ffmpeg にインストールされます。 (Ubuntu)
ただし、snap でインストールした ffmpeg はサンドボックスで動作するため、9VAeの外部ツールとしては使えないようです。sudo snap install ffmpeg
- snap がないといわれた場合 (Ubuntu 14 など)
sudo apt install snapd
この命令で snap がインストールできます。
- 9VAeで作成した MP4動画が再生できない場合、vlc をインストールするとよいです。
sudo apt-get install vlc
- mpg321 を導入すれば、9VAe上で、MP3音楽を利用できるようになります。
sudo apt-get -y install mpg321
midori / Chrome のインストール (Ububtu)
Ubuntu のブラウザ、Firefox が、最初の起動時しか動かないようです。最初に midori や Chrome をインストールしておくとよいでしょう。
- midori (軽量ブラウザ)のインストール。
sudo apt-get install midori
- Chrome のインストール
- ここから Chrome をダウンロード
- ファイルアプリから、ダウンロードフォルダを開く。
- ダウンロードした「google-chrome-stable...deb」を右ボタンでクリック。「ソフトウェアのインストールで開く」を実行。
ChromeOS Flex
- Chrome拡張機能を使ってUSB起動メモリを作成できます。ダウンロードはこちらから
- Chromebook と互換性があり、Googleドキュメントが高速に動きますが、Androidストアアプリは動きません
- 「ChromeOS Flexを試す」ボタンのあと、最初の文章のご自宅利用の場合は「こちら」をクリックすると説明が表示されます。
- Chromeブラウザの拡張機能を起動して、USBメモリを作成します。
- USBメモリをパソコンに挿して起動。最初に読み上げ機能を有効にするか英語できいてきます。どちらでもOK
- 「English」をクリック。Languageを「Japanese - 日本語」、キーボードを「日本語」にして「OK」ボタン
- 「始める」
- 「試してみる」にチェックして「次へ」2回
- Googleアカウント、パスワードを入力。「同意して続行」
9VAeのインストール、しゃべる解説動画の作り方
- ここからUbuntu 64bit版をクリック。右上のダウンロードボタンからZIPをダウンロード。ファイルを選んで右ボタンメニューから「ここに解凍」。Mintでは、9vaフォルダの中の9Viewをダブルクリックするとアニメが再生されます。9va-pi がアニメエディタです。
- しゃべる動画をつくるには、OpenJTalk をインストールします。
sudo apt-get install open-jtalk sudo apt-get install open-jtalk-mecab-naist-jdic sudo apt-get install hts-voice-nitech-jp-atr503-m001 - 女の声は、Meiをいれます。参考文献:OpenJTalkでおしゃべりする
wget https://sourceforge.net/projects/mmdagent/files/MMDAgent_Example/MMDAgent_Example-1.6/MMDAgent_Example-1.6.zip/download -O MMDAgent_Example-1.6.zip
unzip MMDAgent_Example-1.6.zip MMDAgent_Example-1.6/Voice/* sudo cp -r MMDAgent_Example-1.6/Voice/mei/ /usr/share/hts-voice - 上の作業を行ってから9VAeを起動し、文字をいれて、選択枠中央+メニューから「しゃべる」を2回実行すればしゃべります。下の動画に説明があります。
Linux版9VAeは、Windows版よりもフォントがきれい。LibreOffice用アニメGIFも作れるのでおすすめです。
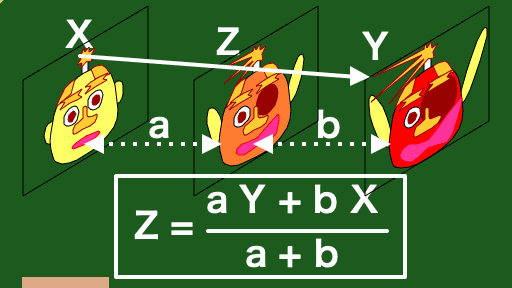
内容:
- Linuxの入手
- Linux起動USBメモリの作り方(Windows用)
- パソコンの起動順序の変更
- Linux Mintの日本語化
- Linux Mint のファイル共有
- FFmpeg / mpg321 のインストール
- midori / Chrome のインストール (Ububtu)
- ChromeOS Flex
- 9VAeのインストール、しゃべる解説動画の作り方
- 解説動画の作り方
解説動画の作り方
この記事のひとコマ解説GIFは、フリーソフト9VAeきゅうべえの「ひとコマ機能」で作成しています。
9VAeきゅうべえのダウンロード
- Android / Chromebook:9VAeきゅうべえAndroid版、9VAeDangla
- iPad / iPhone:9VAeDanga (Apple)、9VAePro (Apple)
- Win / Mac / Linux:無料ソフトでアニメを作ってみよう - Qiita
- Amazon Fire : 9VAeきゅうべえFire版 (Amazon)
- 9VAeのボタン説明、メニュー/キー
上を見るとダウンロード、形の変形、SVGイラストをパーツ化する方法がわかります。
- 9VAeきゅうべえで、キャプチャー画面に、矢印や説明を加え、ページに「ひとコマ」設定するだけで作れます。
- Youtube動画より作成が簡単で、スクロールしなくても見えるのが特長です。
- Youtube 動画にすることもできます。
画面キャプチャ方法
|
||
|
||
|
ライブラリ> Screenshots |
|
| |
|
アルバム> スクリーンショット |
|
ファイル |
|
|
スクリーンショット |
|
|
ダウンロード |
音声合成でしゃべる解説動画の作り方
アニメGIF、動画出力
- 「ファイルメニュー>アニメGIF出力」または「動画出力」で、好きなサイズのアニメGIF または MP4動画 が作成できます。
Win / RaspberryPi / Linux版 でMP4動画を作るには FFmpeg が必要。Youtube解説 - スマホの場合、端末内の「9VAe」フォルダの中に出力されます。フォトアプリで、「端末内の写真>9VAe」で見ることができます。
- アニメGIFは、背景を透明にできます。音がいれられません。
- MP4動画には音が入れられます。Youtubeに投稿できます。Youtubeに投稿する場合、1秒30コマ、高さ720 または 1080 で出力するとよいでしょう。
9VAeをつかえば素材動画が作れる
- 9VAeきゅうべえを使えば、オリジナルの素材動画が簡単に作れます。
- Openclipart や FreeSVG などフリーのSVGイラストをつかって動くキャラクタが作れます。
- 動画編集ソフトで動画に合成できます。
|
OS |
無料動画ソフト |
9VAeで作れる素材 |
|---|---|---|
|
MP4 連番PNG または MP4 |
||
|
MP4 MP4 |
||
|
PowerDirector |
MP4 GIF または MP4 |
作り方
- もっと長いアニメを作ることもできます。以下をご覧ください。
9VAeきゅうべえに関する質問
- 9VAeに関する質問(Yahoo知恵袋)
- よくある質問(Qiita)
- 本記事の文章、図、アニメは複製自由です。教材、解説記事にご利用ください。